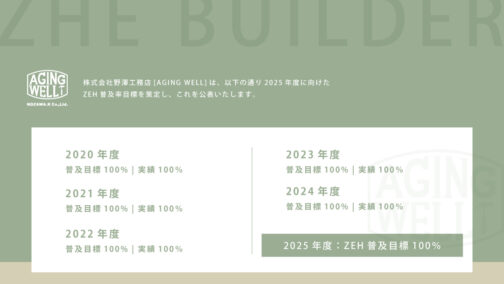こんにちは。南大阪・熊取町にある野澤工務店[AGING WELL]の大工×建築士の野澤星羽です。
梅雨も明け、すっかり夏らしくなってきましたね!
本来ならもう少し早い時期にお伝えすべきことかもしれませんが、最近シロアリ被害の話を耳にしあらためて大切だと感じブログにまとめようと思いました。
今回は羽アリや蟻道を見かけたときに、住まいとどう向き合えばよいのかを簡単にご紹介します。
羽アリはただの虫じゃない?
シロアリは「群飛(ぐんぴ)」といって、巣から羽アリとなって飛び立ち、新しい棲家を探します。
この行動は、湿度の高い春から初夏にかけての時期に多く見られます。
つまり羽アリを見かけたということは「この家、住み心地はどうかな?」とシロアリが下見をしているサインかもしれません。
羽アリの見分け方|シロアリ・黒アリの違いとは?
羽アリ=すべてシロアリというわけではありません。クロアリ(黒アリ)にも羽アリはいます。
ですが、次のような特徴が見られたらシロアリの可能性が高いです。
•胴体にくびれがなく、寸胴な体型
•羽が4枚とも同じ大きさ
•羽がポロポロ落ちている
•見た目は黒っぽい(白くないことも)
苦手でない方はぜひネットで検索してみてください!写真やイラストが沢山出てきます。
見つけたときは、写真で記録を残すことがおすすめです。
ご相談の際状況を正確に伝える手がかりになります。
シロアリの怖さは「気づきにくさ」
シロアリの被害は、壁の中の土台や柱など、目に見えないところで静かに進みます。気づいたときには木がスカスカになっていた…というケースも少なくありません。
さらに、構造材が傷むと建物全体の強度にも影響が出ます。設計や施工がしっかりした家でも、土台を支える部分が損なわれてしまっては、本来の力を発揮できません。
地面からのサイン「蟻道(ぎどう)」も見逃さずに
羽アリが空からのサインなら、地面からのサインとして注意したいのが「蟻道(ぎどう)」です。
これは、シロアリが土や糞、唾液を使って作る「移動用のトンネル」のようなもので、外気や光を避けながら安全に木材までたどり着くための通り道です。
👀 蟻道の目視点検ポイント
•基礎・束石・床下のコンクリート面などに、土が盛り上がったような筋がないか
•基礎の立ち上がりや配管まわりなど、構造のつなぎ目に沿っていないか
•ブロック塀や犬走りとの隙間なども要チェックです
見つけた場合は、無理に壊さず写真で記録を残し、すぐに相談を。
壊すことでシロアリが隠れてしまい、調査が難しくなることもあります。
羽アリや蟻道を見かけたら|まずはこの3つをチェック
1.どこから出てきたか/発生場所を確認
2.羽や蟻道が、周辺にないか見てみる
3.写真で残しておく
これだけでも、被害の早期発見や適切な対応につながります。
シロアリが寄りつきにくい住まいづくり
シロアリが好む条件は、「木材」「湿度」「温度」。
このうち、湿気対策がもっとも効果的な予防策です。
•床下の通気を確保する
•雨漏りや結露を防ぐ
•換気口の前に物を置かない
•古材や木くずを家の近くに置かない
日々の小さな気配りが、シロアリにとって「居心地の悪い環境」をつくり出します。
暮らしを守る「点検」のすすめ
羽アリや蟻道を見かけたとき「そのうちいなくなるかも」「少し様子を見ようかな」と思われることもあるかもしれません。
ですが、小さなサインに早めに気づき、向き合うことが住まいを大きな傷みから守る第一歩です。
シロアリの被害は、放っておくとじわじわと広がり、修復にかかる時間も費用も大きくなってしまうことが少なくありません。
私たちが健康診断を受けるように、住まいにも「点検」というケアが必要です。
草木の手入れやお庭仕事の合間に、家のまわりや床下の様子にも、ぜひそっと目を向けてみてください。
まとめ|羽アリと蟻道は、住まいからの小さな知らせ
•羽アリは、シロアリの活動サインであることがあります
•蟻道は、地面からの“侵入の痕跡”として見逃せないポイント
•目視でのチェックと写真記録が、適格な判断材料と早めの対処につながります
•シロアリ被害は見えづらく、進行すると修復に大きな負担がかかります
•湿気対策・点検・通気確保などの対策は家を長持ちさせるために必要です。
もしご自宅で不安な点や、ご自身では点検が難しいなどありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。